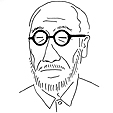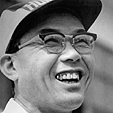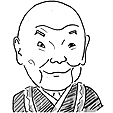金言格言名言集
|
|
(3)永井一正さん1929-「反対がない案から省く」−グラフィックデザイナー 多数決こそ最善の方法と思い込んでいる大衆には「エッ?」と驚嘆させる言葉(というか手法)、お見事! 多くの人が良いと思うものを重ねて、淘汰されて、人類の歴史が出来たわけではない。常識を飛び越えたよう な発想こそが歴史を作ってきた。ただ、そこには才能豊かで洞察力があるジャッジが出来る存在が不可欠で、 私は1964年の東京オリンピック向けのシンボル・マーク指名コンペを思い出す。永井さんも参加して、複 数のデザイナー案から採用されたのは、一番簡単な日の丸をかたどった亀倉雄策さんのデザインでした。選ん だのは勝見勝さんで、勇気ある決断だったと思う。中には田中一光さんの梅の花をモチーフにした優れたデザ インがあり、当時、仮に大衆による投票で選んだら亀倉案は選ばれなかった気がする。似た事例としては永井 さんご自身が関係されたアサヒビールのASAHIは当時の常識を覆し、大成功したロゴデザインである。デ ザインの優劣で、平易なものを選んではならない金言と受け止めたい。 |
|
(5)読み人知らず「最高のものはタダである」 この言葉、東海地区の国道沿いの看板に書かれていた。 付加価値、という言葉に代表されるように、私達は価値が高いものを作ろうとし、価値の高いものが欲しくな る。けど、どれもこれも生きていくための「空気」とか「水」があっての話で、生死をさまようような時には 必要としない。すなわち、「水」や「空気」以上のものは存在せず、しかも、それは基本的にお金を必要とし ない。人に備わっている「愛する」ことも「考える」ことも、「感じる」ことも「作る」こともタタである。 何という言葉だろうと思った。同時に、「たかがデザイン、されどデザイン」を連想させる言葉でもあると思 った。創作物に対して謙虚であることを痛感させられる。 |
(6)浅草の仏壇店「形は心をすすめ、心は形を求める」 心は形に従う。内を変えたければ、外を変える。外を変えたければ、内を変える。 誕生日祝いやバレンタインは愛情を形に変える、あるいは変えた手段である。葬儀も亡くなった人に対する敬 意と死という別れに対する形である。ニワトリが先か、タマゴが先かと言われればニワトリという形にしたも のが先だろう。クルマであれば、昔は高嶺の花だったから、ことさら立派で豪華なデザインが求められ、その 豪華さが、今度は人々の欲望を所有欲を誘った。ファッションであれば、儀式には礼儀に適ったフォーマル服 を求めるし、そのシックなフォーマル服が身のこなしまで誘発させる。晴れ着しかりである。ただ、「それら しい」形は経年により変化する。白もの家電という言葉がある通り、象徴や虚栄心などの感情から離れてしま えば単なる手段に収まってしまう。カラーテレビが高価だった時分には神社仏閣型のデザインが求められたが 、今はただの黒い板である。 |
(7)読み人知らず「名品に重いものなし」 重い方が良い場合もあるが、基本的に、そのものを極めると「重さ」からも解放される。木工では箱などの指 もの、轆轤(ろくろ)物などがそうだし、陶器などの焼き物、グラスなどのガラス製品も突き詰めると薄くな り持って見ると驚くほど軽い場合が多い。ゴツイという言葉があるが、それは名品と真逆の状態を指している 物といえよう。自動車においても部品や仕組みが複雑になり、半世紀の間に随分と大きく、重くなった。が、 今日では軽量化のための考え方や技術が進化して、小型車で300kg近い減量に成功している車種も出て来 た。軽くなると、乗り心地も軽く安っぽくなるが、そこに重厚さを感じさせる技術も実現している。クルマに おいても「名車に重いクルマ無し」になっていくことは間違いなさそうだ。 |
(8)大川 悠さん1944-「さりげなく、さりげあるもの」−元自動車雑誌編集長 「らしい」ことはデザインにとってとても大切である。「女性らしい」とか「男性らしい」という言葉と同義 である。が、あまり「女性らしさを過度にしぐさや化粧」に取り入れてしまうと「媚び」を感じるようになり 、「嫌味」に繋がってしまう。デザインにおいても過分に「らしいデザイン」を強調すると、それがデザイン の主題のようになり、本来の姿を失ってしまう。実に難しい、絶妙なさじ加減がもとめられるが、そこを「さ りげなく、さりげある」ものと表現し、「素っ気無さ」に繋がる前に留まることを示した言葉だと感じる。多 面的な角度から自動車評論・編集を実践した大川さんならではの味がある、素晴らしい言葉だと思う。 |
(9)三原昌平 1947-「売れたことがない、売れるデザイン」 世界でいち早く産業振興、活性化にデザインを取り入れた日本だが、デザインの役割に「生産や販売」を目的 化したことは大失態だった。あれから半世紀以上も経って、少しもその大義名分が改められていない。依然と して才覚がなく、デザインに疎い人達の切り札にされてしまっている。八方美人で万難を廃した、オークマイ ティーなデザインは成功したためしがない。マーケッティングを誤解して、多くの人の意見を取り入れるなど というデザインはあり得ない。皆な「売れて」、「儲かって」、豊かになることを妄想しているので、「売れ るデザイン」は魔法の言葉だが、そんなものは実在しない霊感商法と寸分違わない事を肝に命じるべきである。 万難を廃したデザインはあり得ない。 |
(10)三原昌平 1947-「継続は必ず腐敗する」 間違えてはならない。「継続は力」は個人の話であって、集団や組織、権力は「継続すれば必ず腐敗する」。 例外はない。自分は、自分達は、と考えるべきでない。間違い無く腐敗している。 |
(11)三原昌平 1947-「長いものに巻かれてはならない」 普通は処世術として「長いものに巻かれろ」となるが、工業デザイナーがそんなことで一生を終えることは絶 対にあり得ない。「長いもの」とは既存の価値観を指し、イコール権力である。全てを受け入れて良いデザイ ンなど出来るはずがない。必要は発明の母というが、疑問こそデザインの母であり、疑問が感じなければ新し くデザインする必要はない。物や事柄だけでなく、権威や権力も例外であるべきではなく、打算的に許容する 概念の「長いものに巻かれろ」は著しくデザイナーの自尊を損なうもので、もちろん「長ものになろう」とす る意図や行為は厳に慎むべき、ということになる。少なくても今の日本に「長いもの」は全く必要ない。 |
(12)三原昌平 1947-「手段は直ぐに目的化してしまう」 目的のための手段。この関係は簡単でない。目的を達成した後の「手段」、これを継続したり維持されること が多い。日本の衰退は、この関係と無縁ではない。デザイン関係において観察してみると、1955年前後に 作られた制度や団体がそのまま継続されている場合が多い。中には半世紀前後、その中枢に籍を置いて活動し ている建築家やデザイナーが存在する。あたかも、籍に居座ることが目的であるかのようにさえ映る。特に、 権威が長い時間、不動であることは組織がサロン化し、(9)で書いたように腐敗が確定するという恐ろしい 事態になる。ノークレームであることが異常だし、リフレッシュして新人送りだすバリアであることは間違い ないと考えたい。 |
(13)三原昌平 1947-1991「世の中はホストとゲストで出来ている」 ホストはゲストを招く礼儀をわきまえ、ゲストはホストの尊厳を守らなければならない。招いておいて恥をか かせたり、ゲストに招かれていながらホストを虐げるような行為はいかなる場合も慎むべきである。この問題 、意外とデザイナーは身についてなく、無礼、非礼が度々散見される。また、それぞれの立場における力量に ついては十分に条件に適っていることも必須であることは言うまでもない。 |
|
(15)「失敗は成功のもと」 無印良品が社会に浸透、それにデフレが加わって無駄なものを排除するシンプルなデザイン価値が定着した。 ニトリやダイソー、セリア、カインズ、昨今の新興勢力は似たテイストだ。回り道をしない、達観したテサイ ンだが、一方で冒険や実験、挑戦が抜けてしまいがちであることも事実だ。こじんまりとしていないミッドセ ンチュリー物や、30年前のポストモダンデザインに熱心なファンが存在するのは、デザインの効率にないロ マンや情熱が感じられるからだろうと思う。最終結論は置いておいて、今と異なる形を追い求めるのがデザイ ンと考えたい。 |
(16)柏木 博さん「パソコンを見ることは、自分の脳を見ること」−デザイン評論家 1990年代初め、自動車雑誌で語った言葉。現代の「仕事」の形を予見するものでもあった。今日では、ス マホの方が発達しているので「パソコン」という単語は「スマホ」に置き換わっているかもしれない。混雑し た電車の中、休憩時間、待ち合わせ時間、帰宅しての寛いだ時間。私達は「脳」と連携した「スマホ」とか、 「バソコン」を見ている。働くことはパソコンであり、情報を得ることはイコール「スマホ(バソコン)」で ある。小説を書く事も、機械を設計することもバソコン、疑問を解決することもパソコン(スマホ)なのだ。 こうなると、逆に、昔は「パソコンで絵が描けない」ことが問題視されたが、現代においては「パソコンから 外れた絵が描けない」ことが課題になりそうで、そこを見抜けた者だけが次の世界を開く事が出来るだろう。 |
(17)ルネ・マグリット1898-1967「見えているものは、見えていないものを隠している」−画家 デカルト哲学のような言葉だが、シュルレアリスム絵画「白紙委任状」の解説に登場する。マグリット自身が 見えている物を描こうとせず、頭の中で見ようとしたものを描いた作家だったが、その代表作である作品にピ ッタリとあてはまる言葉だと言えよう。私達を取り巻く視覚だけでなく、情報や様々な事象を理解する言葉と して、これ以上相応しい言葉を私は知らない。特に「権威」が「権力」に様変わりしている姿を洞察するため の溶剤として捉えたいと思う。 |
(18)シャルロット・ペリアンさん1903-1999「日本人には批判精神が足りない。(特に若者)」 戦前、戦後を通して日本と交流があった氏は、時代の変化と日本の姿を目のあたりにしてきた。日本がペリア ンから刺激や影響を受け、ペリアンも日本の文化の影響を受けている。上記の発言はむ1980年代前半のも のである。その指摘の的確生は、30年以上経った今の日本の姿であり、若者の行動様式でさえあることが悲 しい。私が、この言葉に付け加えるとすれば、疑問を持てないから批評、批判で出来ない、ということに尽き ると思う。出来上がった価値観に従順なだけでは時代は切り開けない。 |
(19)水野和敏さん1952-「過去は言葉になるが、言葉で未来は作れない」 日産GT−R (R35)の開発者として知られる水野さんは、試乗レポートなどにおいても丁寧な言葉での解説が 読者をひきつけるが、現場主義として、言葉では空回りしてしまい、未来を創造することは出来ないと説いて いる。レポートに頻繁に出て来る開発過程での実車「走り込み」の重要性はそうした視点からに違いない。 |
|
|
(22)丹下健三さん1913-2005「これからはずぅっとポストモダンだ」建築家 数多くの名作と革新性にチャレンジした丹下さんのポストモダンの定義は通俗的なそれとは違うかもしれない が、完成度を二の次に捉えるイメージのあるので、やや意外な言葉にも受け取れる。常にリフレッシュして、 建築を考えなさいと諭されていると受け取りたい。 |
|
(24)新約聖書「新しい酒は新しい革袋に盛れ」 プロダクトデザイナーにとって耳が痛い言葉。有名ブランドとか、誰かが開発した手法とか製造機関で作る ことを目標にしてしまいがち。それしか視野に入らない了見の狭さとか、新しい考え方に欠如していること が端的に表れてしまっている思考、行動。勉強のためであれば、遅くとも30才中頃には卒業したい。これ は事例が多すぎて気の毒になる。 |
|
(26)鶏口牛後「鶏口となるも牛後となるなかれ」 デザイナー、特に工業デザイナーには耳が痛い熟語だろう。 不安定で、根拠に乏しく、吹けば飛ぶような存在、鶏と、安定し、大きな存在の牛。どちらが良いか。 例えば学生の就職活動においては、時代にあった大手企業に人気が集中する。 片や、特徴があって文化的であっても中小企業は敬遠されるし、それが零細企業だったら尚更である。 さらに進んで、信念をもって、その実現のために独立することの勇気をどれくらいの若者が志しているか。 この熟語は試験問題にも出るし、多くの学生が言葉として正しく理解出来ているはずだが、人生において実 行出来る者は希である。 デザイン学科を卒業すれば「芸術学士」である。平易に言えば感覚やスキキライが伴う。この熟語は重い。 |
岡倉天心・柳 宗悦・三原昌平
2019 Syohei mihara design studio.All right reserved.